『史学雑誌』「2019年の歴史学界—回顧と展望—」
今年も「回顧と展望」が出ました。以下、ざっと目を通した箇所を列挙していきます。
総説(高山博)
2020年春頃までに関する新型コロナウイルスの動向を、日本、中国、台湾、国際機関などに言及しながら整理しているが、あまり歴史学界とは関係ない内容。「コロナ後の世界」として、①インターネットの世界(電脳空間)のさらなる拡大と②国家の重要性の再認識を強調しており、これらは著者がこれまで折りに触れて言及してきたことである。すでにユヴァル・ノア・ハラリや大澤真幸らは国家単位では最終的にパンデミックへの対応はできないことを論じているのだが、今後の展開に注目。
歴史理論(北村厚)
2022年度から高等学校で「歴史総合」が導入されることを受けて、高大連係の中でいかなる教育が求められるかを見定めることが喫緊の課題である。歴史学とはどのような可能性を持つ学問かを改めて問うた著書が紹介され、リン・ハント『なぜ歴史を学ぶのか』のシティズンシップ教育を受けてのパブリック・ヒストリー(公共歴史学)、さらにはしばらく関連書籍が出続けているグローバル・ヒストリーについて言及。確かに、ミネルヴァの<MINERVA世界史叢書>、山川の<歴史の転換期>シリーズは良書が出ているようだ。
ヨーロッパ(中世—一般)(岡崎敦)
冒頭で一般的傾向として①学界の世界標準化、②共同研究、③学問の社会的危機(就職難、社会的関心の低下)を取り上げる。危機意識が伝わる内容となっており、「研究史の脱構築と比較の視座という日本の西洋研究独自の戦略的スタンスを、どのように維持するかが、いまあらためて問われている」と結ぶ。
ヨーロッパ(中世—西欧・南欧)(黒田祐我)
紹介されている文献を眺めるに大変充実した一年になっているように思われるが、末尾で若手研究者の数が激減していることを大いに危惧している。「『ユニバーサルな学問共同体』に参画していきながら、・・・魅惑的かつ壮大なビジョンをいかにして日本の社会と教育現場に提示できるか」というのは我々共通の課題であろう。
ヨーロッパ(中世—中東欧・北欧)(田口正樹)
過去15年間の本欄を読み返したところ、全体の研究業績数は2000年代末から減少傾向が見え始め、2010年代に入ってからは新規参入する若手研究者が少なくなっているとのこと。これはしかし中世ヨーロッパ史全体の傾向なのだろう。末尾では研究分野としての「論争の少なさ」を指摘しており、これは結構大きな問題なのではないかと再認識した次第。
なお、ヨーロッパ(中世—一般)とヨーロッパ(中世—中東欧・北欧)で拙著Orval und Himmerodが紹介されています。とりわけ田口先生には論文「中世ヨーロッパの修道院における看取り」(本村昌文他編著『老い』所収)も含め、的確に概要をまとめていただきました。
そのほか、文献目録(西洋史II)には、拙訳書『中世共同体論』について岩波敦子と渡邊雄一による書評、江川由布子による合評会の報告が収録されています。
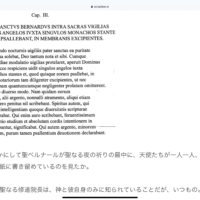





この記事へのコメントはありません。