史料について
珍しく連続して投稿しますが、そのtwitter上で史料中心の実証研究を行うべしという、歴史研究者として至極当然のことをつぶやいたところ、思いがけず議論が広がって大変有意義な経験をしました。最終的に自分としては
1)職人的な姿勢で史料に沈潜した上で、2)そこから抽出したものを歴史的コンテクストに位置付け、・・・無味乾燥な言葉ではない・・・表現・方法で叙述し、伝える。この2段階があるのだと思います。これらは歴史研究者の営みの両輪で、二者択一ではありません。
としました。自分は1)を歴史研究者の最も重要な役割だと認識しているためあえてこの部分を強調したのですが、2)に主眼がある方々にとっては無味乾燥で「so what?」として理解されたかもしれません。この点をadamtakahashiさんは以下のように比喩的に表現してくれました。
「史料中心の歴史学の手法」が重要だということは何度も強調した上でも、それでもなお「原始的で職人的なのは自明」とか言われると、「照明も冷暖房もない部屋」に通されて「造りは丈夫だから、地震に耐えれば良いでしょ」みたいな感じで強要されている気が少なくとも私はします。でも、そういう造りが頑丈なだけの家に誰が住みたいのだろうか。
上手な比喩。上の整理に基づけば、2)をおろそかにすると読み手にとって寒々しい歴史叙述になってしまうということですね。西洋史で言えば、とりわけ初期中世のようにこれまで多くの研究者によって手垢のついた史料を操作しなければならない時、2)で研究者個人の能力が試されるのではないかと思います。
しかし、なぜあえて1)を重視する発言をするかというと、一般史において、古代史〜初期中世史のように史料がちゃんと刊行され多くの研究者の目を通過している時代はむしろ例外的で、大半の史料は精読の余地があるにも関わらず誰の目にも留まらず文書館に眠っています。したがってこれはドイツ、あるいはドイツの地域史研究の伝統なのかもしれませんが、極論を言えば1)だけでも評価されるように思います。一つ一つは無味乾燥かもしれませんが、そうした知の蓄積は、結果として妥当性のある一般論を導き、時代をより正確に理解するための一助として評価するわけです。さらに言えば、こうした個別研究は研究者養成の目的から博士候補生らが担い、毎年数えきれないほどの単著となって世に出ます(ドイツでは、博論を出版しないと正式にDr.を名乗れません)。
翻って自分の研究がどうなのかと言えば、明らかにこうした地域史研究の伝統の中にいると自覚しています。今後研究をどう発展させるかはひとまず棚上げして、博論ではとにかくその中でできるだけ多くの証書史料を読みこなしていこうと思っています。そういう意味でひたすら「職人的」な作業を毎日しているわけです。ただ方法論上なんの特色もないかというとさにあらずで、自分が師事しているA. Haverkamp先生が常日頃強調するのは、単なる制度史・政治史ではダメだ、ということです。常に中世社会の共同体形成や人々の宗教的メンタリティを重視するのですが、先生の一連のユダヤ史研究、あるいは例えば
Leben in Gemeinschaften: alte und neue Formen im 12. Jahrhundert: in: Aufbruch – Wandel – Erneuerung. Beiträge zur „Renaissance“ des 12. Jahrhunders, hg. v. G. Wieland, Bad Cannstatt 1995, S. 11–44
Neue Formen von Bindung und Ausgrenzung. Konzepte und Gestaltungen von Gemein- schaften an der Wende zum 12. Jahrhundert, in: Salisches Kaisertum und neues Europa in der Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V., hg. v. B. Schneidmüller und S. Weinfurter, Darmstadt 2007, S. 85–122
などを参照すると分かりやすいかもしれません。こうした視点を大いに参考にしながら、地域内におけるシトー会修道院の社会的・宗教的機能を明らかにしようとしています。シトー会修道院がらみの経済史研究は沢山あるので、そこからも距離を置く感じで。この辺、一昨年の学振の申請書に書いたような気がする(笑)
なんともまとまりのない文章でしたがひとまずこの辺で。一通り自分の現在のスタンスを言葉にしてみました。

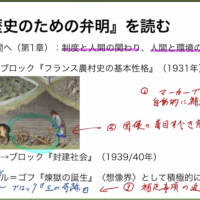

この記事へのコメントはありません。